AWARDS東川賞
第41回写真の町東川賞 受賞者
海外作家賞
国内作家賞
新人作家賞
特別作家賞
飛彈野数右衛門賞
第41回審査会委員
安 珠[あんじゅ]写真家
上野 修[うえの・おさむ]写真評論家
神山亮子[かみやま・りょうこ]学芸員・戦後日本美術史研究
北野 謙[きたの・けん]写真家
小原真史[こはら・まさし]キュレーター・東京工芸大学准教授
柴崎友香[しばさき・ともか]小説家
丹羽晴美[にわ・はるみ]学芸員・写真論
原 耕一[はら・こういち]アートディレクター
<敬称略/五十音順>
第41回写真の町東川賞審査講評
第41回写真の町東川賞審査会は、2025年2月20日に開催された。今年ノミネートされたのは、国内作家賞39名、新人作家賞45名、特別作家賞20名、飛彈野数右衛門賞31名、海外作家賞15名。例年どおり、午前中は写真集や資料をじっくりと閲覧し、午後から審査会委員8名が合計140名(延べ150名)の作家より5つの賞を選ぶ審査に入った。
国内作家賞は、最終段階で4名に絞り込まれた。この段階になると甲乙つけ難い、異なった魅力を持つ作家が並ぶことになる。熟考を重ね、議論と投票を繰り返した結果、僅差で今道子氏が選ばれた。今氏は、2021年から2022年にかけて神奈川県立近代美術館 鎌倉別館で開催された大規模な個展「フィリア―今 道子」で注目を集めたが、今回の審査では、モチーフとオブジェの幅を広げ、死生観をさらに掘り下げた新作も大きく評価された。1987年の第3回東川賞新人作家賞の受賞者でもある今氏が、40年弱の年月を隔て、新たな展開で国内作家賞に輝いたことを喜びたい。
毎年、混戦かつ接戦となる新人作家賞だが、今年は、13名に絞り込んだ段階の投票で多くの票を集めた鈴木のぞみ氏に決定した。鈴木氏は、日常の事物に潜む像を、写真の原理によって顕在化する試みを続けている。「光の言葉」の媒介者・翻訳者であれたらという鈴木氏のアプローチは、近代の産業の発展を体現するメディウムでもある写真によって、見る見られるという権力的な構造を重層的に照らし出す。歴史的・社会的出来事と個人的な記憶を繊細に織り成しつつ、大きな物語と小さな物語をダイナミックに交叉させていく近年の展開は、新人作家賞にふさわしいものだろう。
特別作家賞に選ばれたのは、第二次世界大戦末期アメリカ軍の侵攻を想定し、終戦まで急造されたが実際に使われることはなかった、北海道東沿岸部に点在する戦争遺構のトーチカをリサーチした守屋友樹氏である。風景と敵に対する眼差しについて考えるようになった守屋氏は、トーチカをピンホール・ルームにし、銃眼と呼ばれる敵を撃つために設けられた小さな窓から見える風景を像としてフィルムとノートに写した。この「潮騒の部屋」シリーズが、東川町文化ギャラリーの受賞作家作品展でどのような眼差しを浮かび上がらせるのかということにも、期待が膨らむ。
飛彈野数右衛門賞は、戦後米軍に占領された沖縄・伊江島で農民たちと共に非暴力の土地闘争を行った阿波根昌鴻氏に決定した。阿波根氏は、強制的な土地接収や米軍の横暴を記録するために1955年から撮影をはじめ、島で唯一のカメラを米軍に抵抗する手段として活用していったことで知られている。2024年に開催された展覧会「阿波根昌鴻 写真と抵抗、そして島の人々」は、遺されたネガ約3200枚をデジタル化し、日常のスナップや住民たちのポートレイトを含めて構成されたものであり、平和運動家としての阿波根氏の活動のアクチュアリティを現在へとつなげるものだった。
海外作家賞は、菊田樹子氏の調査に基づいた丁寧な説明を踏まえたうえで審査に移り、対象国のリトアニアから、アルトゥーラス・ヴァリャウガ氏が選ばれた。ヴァリャウガ氏の作品は、移民、バルト海を渡り大学や仕事に行く人々、ドイツとソビエトに翻弄され続ける小さな町、原発のある村など、さまざまな被写体から、リトアニア人とは誰のことを指すのか、そのアイデンティティについて問いを提示する。失われた過去へのノスタルジーや悔恨ではなく、何が変わったのか、なぜ変わったのかを、冷静に検証しようとしている展開が高く評価された。
今回で第41回となる写真の町東川賞だが、その特徴は、毎年夏、授賞式と同時に作品展やシンポジウム、受賞者と交流するパーティなどが開催されることにある。われわれも、どこかでその東川町フォトフェスタの空間を思い描きながら審査をすすめている。つまり東川賞の審査は、その日だけで完結するものではなく、現在、そして過去と未来の東川町フォトフェスタに接続されているといえよう。1985年の「写真の町宣言」から、2014年の「写真文化首都宣言」を経て現在に至るまでその空間を作り上げ続けている、町の人々の多大な努力と共感に深く感謝したい。
写真の町東川賞審査会委員 上野 修
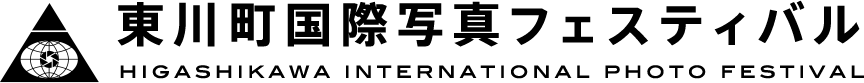



-scaled.jpg)


-scaled.jpg)
